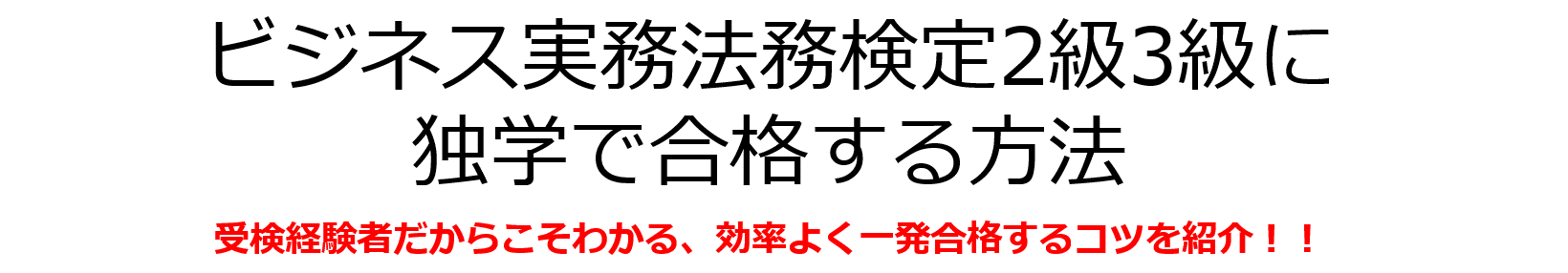昨今のグローバル化を受け、日本国内の会社も海外で取引、支社設立をするケースが増えてきました。そうした場合問題になるのが、トラブルがあったときいずれの国の法律を採用するか?という点。本記事ではそんな国際取引契約のルールについてみていきます。
昨今のグローバル化を受け、日本国内の会社も海外で取引、支社設立をするケースが増えてきました。そうした場合問題になるのが、トラブルがあったときいずれの国の法律を採用するか?という点。本記事ではそんな国際取引契約のルールについてみていきます。
国際取引契約と国内法の違い
| 項目 | 概要 |
| ①国際裁判管轄ルール | 主に以下の場合、日本の裁判所に管轄権が認められる (1)主たる事業所・営業所が日本国内にあるとき (2)契約で定める債務の履行地が日本国内にあるとき |
| ②準拠法 | 国際取引に係る紛争の解決にあたり、適用される法律のこと。 ・当事者自治の原則を採用。(準拠法選択の決定を、当事者の意思にゆだねる) →合意が得られなかったとき:最密接関係地法を採用 (=当該法律行為に最も密接な関係がある地の法を採用) |
| ③外国判決の執行 | 外国判決の内容を、日本国内で執行する場合の要件: ・外国判決が確定していること ・日本国内の裁判所でも、執行判決を得ること →法令・条約等で、外国裁判所の裁判権が認められることが必要 |
| ④仲裁 | 仲裁人(第三者)の仲裁裁定には、確定判決同様の拘束力が与えられる ・仲裁合意:当事者全員が署名した文書が必須 ・メリット:適任の専門家を選定できる、手続きを簡略化できる ・離婚の紛争等は対象外 |
| ⑤アメリカの司法体系 | (1)州法の位置づけ: 州法が民事問題全般を規律 (2)ロングアーム法: 被告の活動が、当該州と少しでも関与していれば、裁判所は裁判権を持つ。 (3)契約の成立条件: 当事者の合意だけでなく、約因(=拘束力の根拠)が必要 (4)裁判の事前手続き: 原告・被告は、事前に証拠の開示が必要(=ディスカバリー) →争点の明確化、および早期の和解に寄与 (5)フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理(不便宜法定地) →適切な裁判所で訴訟をやり直させるため、裁判所が訴えを却下できる |