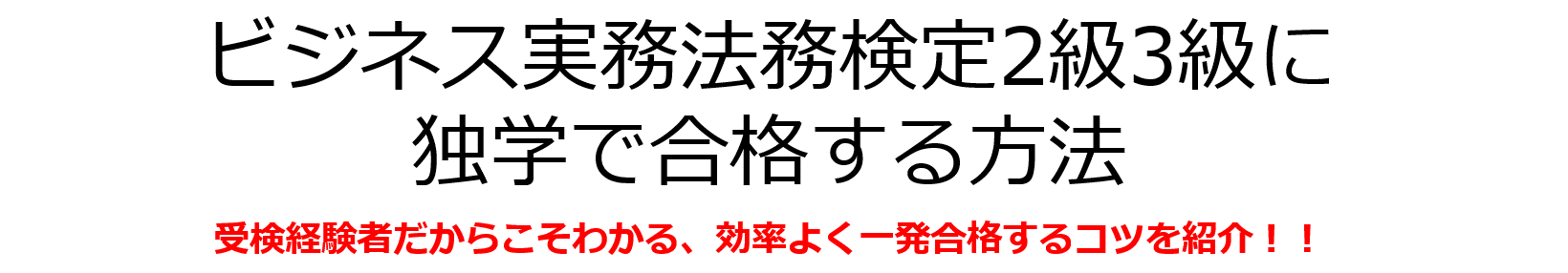民事訴訟の前後を問わず、債権者は、裁判により自身の権利を保全することができます。これは民事保全法に規定されている権利であり、「仮差押え」「係争物に関する仮処分」「仮の地位を定める仮処分」などが規定されています。それぞれについて確認していきましょう。
仮差押えと仮処分の違いとは
| ①趣旨 | 債権者の(将来的な)強制執行権の保全。 ※裁判必須! →民事訴訟の前後を問わない |
|
| ②保全手続の種類 | (1)仮差押え | ・民事執行上の「差押え」の準備段階。 対象:金銭債権のみ (債務者が勝手に消費しないように) =一定の被保全権利・保全の必要性がある場合 |
| (2)係争物に関する仮処分 | ・非金銭債権のうち、物に対して実施 | |
| (3)仮の地位を定める仮処分 | ・非金銭債権のうち、物以外に対して実施 (役職等) ※金銭債権を対象としてもOK |
|
| ③仮差押え の目的物 |
目的物は以下でもOK (1) 条件付きor期限付き債権 (2)目的物が特定されていない動産 ※相手の自宅に何があるか,特定困難なため (3)裁判所命令による担保の設定 |
|
| ④要件 | (1)債権があること(弁済期限は到来していなくてもOK) (2)債権者が、目的物保全の必要性を疎明すること (3)債権者が担保(保証金の供託)を立てること : 債務者が被りうる損害の担保として。 |
|
| ⑤効力 | ・第三債務者は、債務者に弁済しても、そのことを債権者に対抗できない ・仮差押えには優先弁済効力なし: ・他の債権者の強制執行は妨げることができない ・第三債務者から債権者への、直接弁済を請求することも不可。(あくまで保全のみ!) |
|