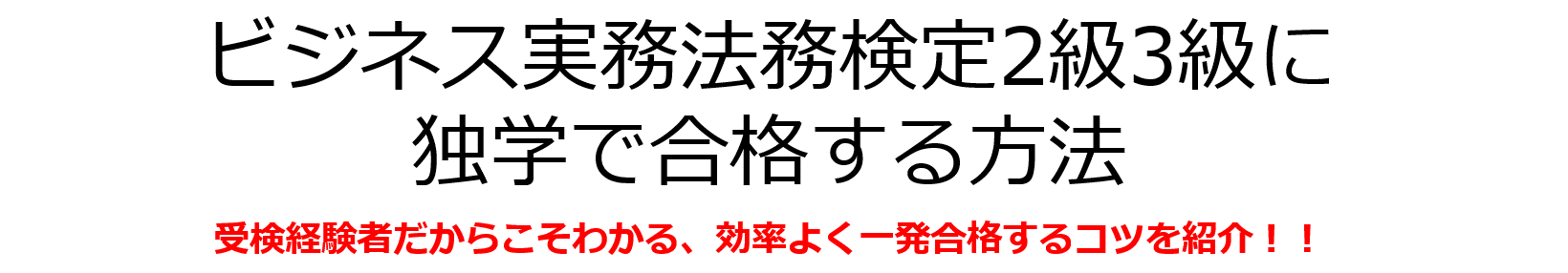消費者の利益を守ることを目的として、消費者契約法が存在します。
消費者の利益を守ることを目的として、消費者契約法が存在します。
消費者契約法そのものの内容もさることながら、試験で聞かれるのが取消と無効の違い。行為によって、取消となるものと無効となるものがありますので、その違いをしっかりおさえていきましょう。
消費者契約法の目的と対象
| ① 目的 | 消費者側の利益を守るため、消費者が誤認・困惑した場合のフォローをすること。事業者に努力義務が課される(⇔法定義務) |
| ② 対象 | 消費者と事業者の間で締結される契約すべて ※貸金業法に規定がある場合は、そちらが優先される |
| ③ 用語の定義 | ・消費者 : 個人のみ(法人・個人事業主は該当しない) ・事業者 : 個人+法人+個人事業主 ※営利目的かどうかは不問 |
消費者契約法で取消できる行為の例
| ① 取消できる行為 | 事業者の以下の行為で消費者が誤認・困惑し、うっかり申込・承諾してしまったとき
[誤認] |
| ② 取消の効果 | (1)契約:遡及的に無効となる(=初めからなかったことになる) (2)消費者/事業者の義務:双方とも、原状回復義務を負う →消費者側は、取消までの期間の使用料等を支払わないといけないケースあり |
| ③ 時効 | 以下のいずれか (1)消費者が誤認・困惑に気づいてから6カ月 ⇔民法:5年 (2)契約締結から5年 ⇔民法:20年 |
消費者契約法で無効となる契約条項の例
・(相対的に力の強い)事業者が、不当に消費者の利益を奪うものは無効。
・無効となる例:
| 無効となる契約条項の例 | |
| ① 事業者の債務不履行時 | [原則]事業者の賠償責任免除 → 無効 [例外]事業者が善意無過失のとき → 賠償責任の”一部免除”は有効 |
| ② 目的物に瑕疵があるとき | [原則]事業者の賠償責任免除 →無効 [例外]事業者が、別に修補責任等を負うとき →”賠償”責任は免除可能 |
| ③ 解約違約金 | 平均的な損害額を超える金額の請求 →無効 (例)ホテル予約を6カ月前にキャンセルしたのに、キャンセル料50%など |
| ④ 遅延利息 | [原則]法定利率14.6%を超える部分 → 無効 [例外]金銭貸付時:20.0%を超える部分が無効(利息制限法が適用される) |