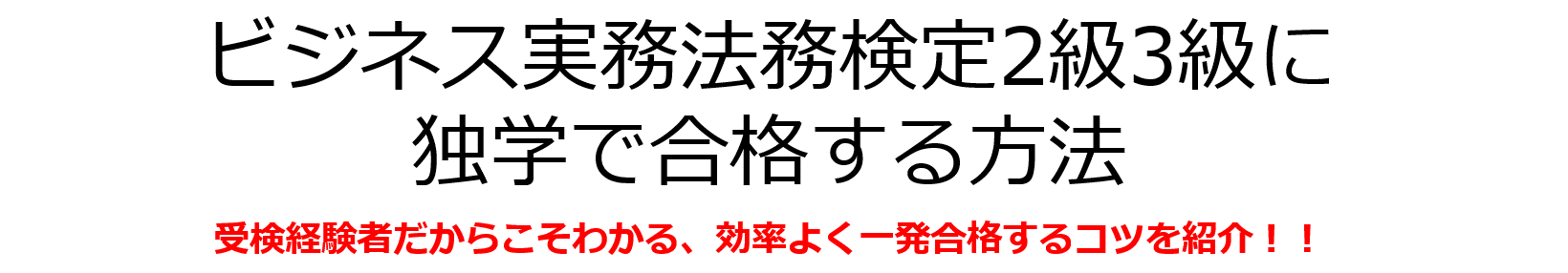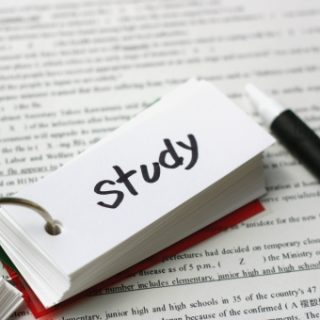 投稿
投稿 ビジ法2級 受検まとめノートを公開します
突然ですが、みなさんは学生時代、どのようにテスト勉強していましたか?私はテスト前になると、ノートや教科書のポイントをまとめ直すタイプでした。要点だけを何枚かのルーズリーフにまとめて持ち歩き、暗記や復習に使う というのが、私の勉強スタイル...
 み-民法
み-民法 弁済の任意代位、法定代位とは
>民法で認められる第三者の弁済のうち、保証人等は民法上も債務者と認められているため、弁済と同時に担保・抵当等も消滅します。一方、親が子供の借金を弁済するケースなどは、その弁済が有効であることを明確にする必要があります。これを第三者が代位するといい、この要件が民法で定められています。
 み-民法
み-民法 弁済の場所・順序のルール
お金を返す、等の弁済行為にあたっては、債権者⇔債務者間で有利不利が発生しないよう民法で規定されています。極端な例だと、「返済は海外で手渡しで行う」と契約書に記載されてしまったら、債務者は弁済が難しいためです。そこで、本記事ではそうした民法上の規定を確認していきます。
 み-民法
み-民法 第三者・準占有者の弁済可否
弁済は、原則債務者のみが行うことのできる行為であり、第三者の弁済は禁止されています。そこでこの記事では、そんな第三者弁済が認められるケースを確認していきます。
 み-民法
み-民法 所有権留保と譲渡留保の違いとは
一括払いではない方法で商品を購入するときなどに、所有権留保という手段が使われることがあります。一方、似た用語で譲渡留保というキーワードもあり、この2つを混同しがち。そこでこの記事では、それぞれの違いを具体例を用いて確認していきます。
 み-民事保全法
み-民事保全法 仮差押えと仮処分の違いとは
民事訴訟の前後を問わず、債権者は、裁判により自身の権利を保全することができます。これは民事保全法に規定されている権利であり、「仮差押え」「係争物に関する仮処分」「仮の地位を定める仮処分」などが規定されています。それぞれについて確認していきましょう。
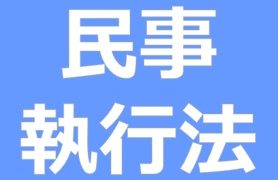 み-民事執行法
み-民事執行法 強制執行の流れと要件
民事執行法に定める要件を充たすと、強制執行のプロセスが開始します。ここでは、裁判で勝訴したのち、どのようなプロセスで強制執行が行われているかかを確認していきましょう。
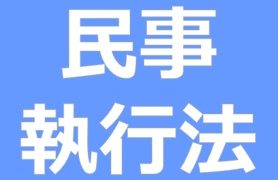 み-民事執行法
み-民事執行法 民事執行の要件と債務名義とは
民事訴訟が「訴えに対して、裁判所が判決を下すプロセス」であるのに対し、民事執行は「債権者が勝訴したのち、取立請求を行うプロセス」です。ここでは民事執行法が定める民事執行のルールについて確認していきます。
 み-民事訴訟法
み-民事訴訟法 少額訴訟と支払督促の違いとは
簡易裁判所における民事訴訟は、判決までのプロセス効率化・簡略化が図られています。そして、さらなる訴訟簡便化のため、日本には少額訴訟・支払督促という制度が設けられています。これは審理回数等の点で他の訴訟よりスピーディな決着が見込まれる制度。具体的に確認していきましょう。
 み-民事訴訟法
み-民事訴訟法 簡易裁判所における民事訴訟
債務不履行ののち、当事者間で決着がつかない場合は裁判所での訴訟に移行します。この時、訴状の提出先は金額により定められており、少額の場合は簡易裁判所にて民事訴訟が行われます。そこで、簡易裁判所で訴訟を行う場合の特徴について確認していきましょう。