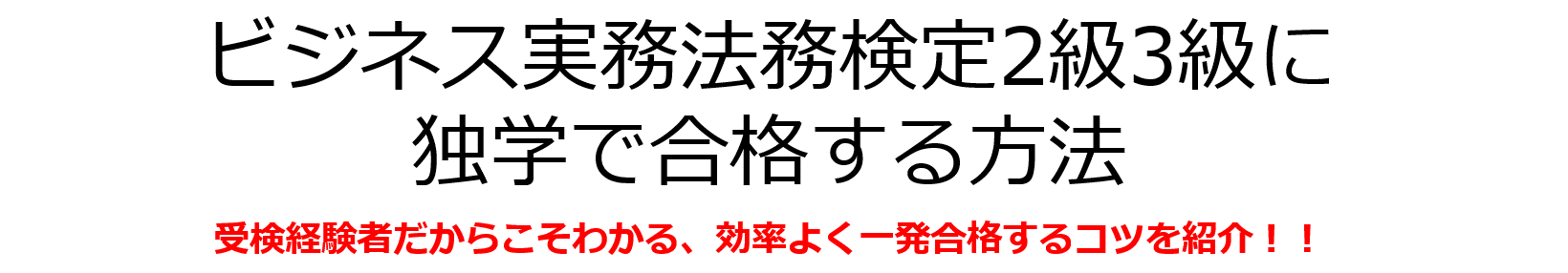お金を返す、等の弁済行為にあたっては、債権者⇔債務者間で有利不利が発生しないよう民法で規定されています。
極端な例だと、「返済は海外で手渡しで行う」と契約書に記載されてしまったら、債務者は弁済が難しいためです。
そこで、本記事ではそうした民法上の規定を確認していきます。
弁済の場所と費用
| 原則 | 例外 | |
| 場所 | 持参債務 (債権者の住所/営業所で弁済) |
①特約設定可能 ②特定物:取立債務(債務者の住所/営業所で弁済) →不動産等。こちらも特約で排除可能 |
| 弁済費用 | 債務者負担 | 特約設定可能(例:交通費一部支給 など) |
| 契約費用 | 当事者折半 | 特約設定可能 |
弁済の充当順序 (返す順番)
| 原則 | ①費用 → ②利息 → ③元本 の順 |
| 複数債務の とき |
① 弁済者が返済順序を指定可能 ② (①がないとき)債権者が指定可能 ③ (①②がないとき)弁済者に有利なもの(下記)を優先 ・期限が過ぎており、遅延利息等が発生してしまっているもの ・利息が高いもの ・期日が近いもの ④ (それでも決まらない時)各債務額に応じて按分 |