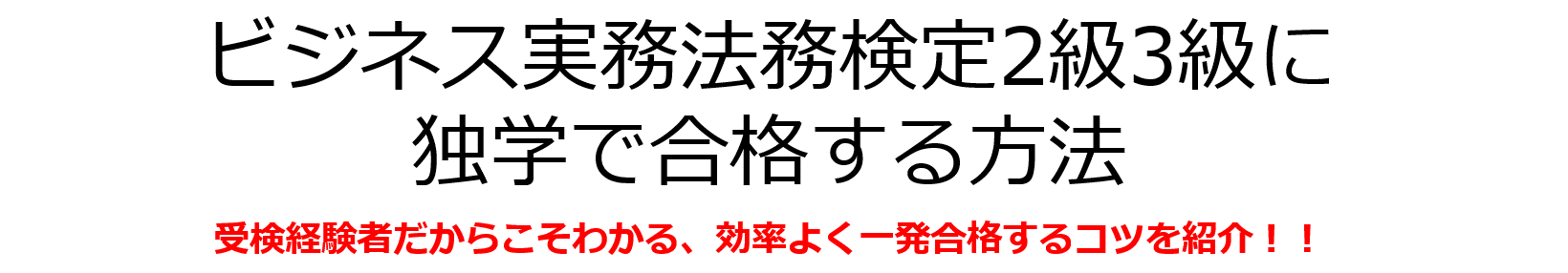独占禁止法は、「公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」を目的に制定された法律。
それでは、具体的な制限内容を見ていきましょう。
独占禁止法 主な制限内容
| ① 私的独占 他事業者の活動を排除・支配すること |
公共の利益に反する行為はNG |
| ② 不当な取引制限 他事業者と共同で、相互の活動を拘束・遂行すること(カルテル) |
以下のいずれかに該当する場合 |
| (1)相互拘束: 紳士協定等も対象 |
|
| (2)共同遂行: 談合等,「行為の外形一致」「事業者間の意思連絡」がある時 |
|
| ③ 不公正な取引方法 不公正な競争で有利に立とうとすること |
(1) 一般指定: あらゆる業種に一般的に適用されるもの |
| ・共同の取引拒絶: ある事業者との取引を制限・拒絶すること |
|
| ・事業者団体における差別的取扱い等: 参入制限行為 |
|
| ・抱き合わせ販売 | |
| ・再販売価格の拘束 (“希望”販売価格の提示等はOK) | |
| ・優先的地位の濫用: 押付販売、協賛金の強制など |
|
| (2) 特定指定: 特定業種にのみ適用されるもの |
違反時の措置
| 措置 | 目的 | 補足 |
| ①排除措置命令 | 違反行為をやめさせるため | <事前に>意見・証拠を提示する機会を与えることが必要
(いきなりは命令出せない) |
| ②課徴金納付命令 | 課徴金を払わせるため | 排除措置命令に従わず、違反を繰り返したときは課徴金命令
・減免制度あり(リニエンシー):自白すれば5社まで減免 ・早く自白した会社ほど、課徴金の免除額も大きい (1番は最大で100%免除) ・公取の調査開始後は、減免されるのは3社まで ・例外:“優先的地位の濫用”は一発アウト |
| ③損害賠償請求 | 損害を受けたものへの救済 | 救済規定なし(無過失責任) |