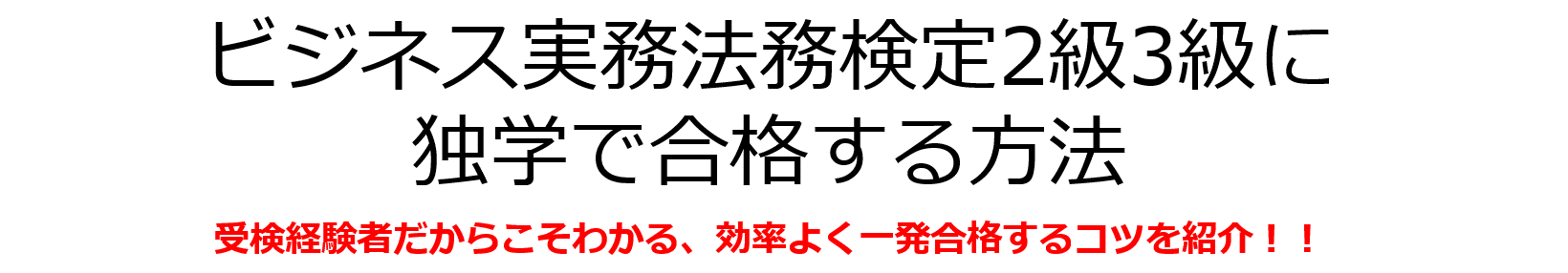不動産などは資産ですから、お金を借りるときに不動産を担保とすることができます。これを抵当・抵当権といいますが、この抵当権についても民法で対象や対抗要件が定められています。細かく確認していきましょう。
不動産などは資産ですから、お金を借りるときに不動産を担保とすることができます。これを抵当・抵当権といいますが、この抵当権についても民法で対象や対抗要件が定められています。細かく確認していきましょう。
抵当権の意義と果実への効力
抵当権の意義
| ①対象 | ・不動産のほか、地上権/永小作権も設定可能 ・土地と建物は別個独立の不動産とみなす |
| ・付帯一体物も対象→借地権/増築部分/玄関の扉など ・従物も対象(抵当権設定時に、既に存在していたもののみ) →畳/冷暖房器具など、不動産の効用を助ける関係にあるもの |
|
| 債権者:元本+最後の2年分の利息に対してのみ、抵当権行使可能 債務者/物上保証人:制限なし |
|
| ②抵当権設定者 | 債務者、または債務車以外の第三者(物上保証人) |
| ③使用・収益権 | 抵当権設定者が保有→抵当対象の不動産収益も、弁済に回せるので合理的 |
| ④設定要件 | 当事者の合意 |
| ⑤対抗要件 | 登記(優先関係は登記順) ※日本は、順位上昇の原則を採用 →先順位の抵当権者が弁済完了すると、後順位の抵当権者が繰り上がる |
| ⑥先順位者弁済時の 後順位者の権利 |
後順位者も、抵当権の実行が可能(利益遺失を避けるため) ・実行しない場合、後順位者の抵当権は消滅 →債務者視点:競売後、改めて抵当権を請求されたら苦しいため ・先順位者の弁済に全額使用されてしまった場合などは、実行不可 |
果実に対する抵当権の効力
| 天然果実 | 法定果実 | |
| ①主な項目 | 野菜・果物など | 賃料・利息など |
| ②効力:債務不履行後に生じた果実 | 及ぶ | 及ぶ |
| ③効力:債務不履行前に生じた果実 | 及ばない | 及ぶ ※物上代位性の観点 |
[要確認]法定果実(賃料等)は、実質不動産と一体不可分とみなされる→③でも抵当権対象とできる
抵当権侵害
・占有屋B(債務者Aとグル)が、抵当権の対象物件を不法占拠している場合
→原則:債権者Cは、占有屋Bを除外不可 ※不動産の使用収益権は、債務者Aが保有しているため
→債権者Cは、「抵当権侵害=抵当権に基づく妨害排除請求」であれば可能
=「抵当権の実行が妨げられている」という切り口でアプローチ